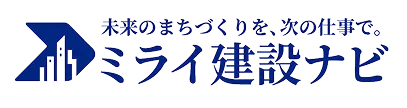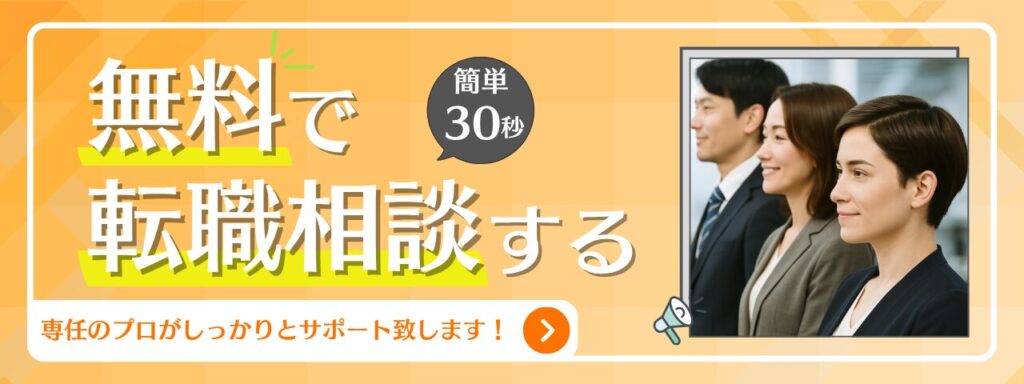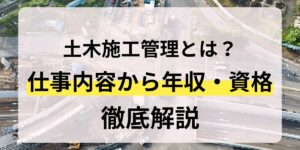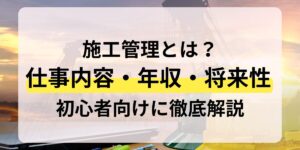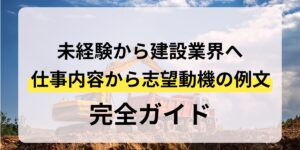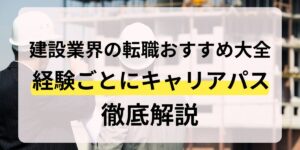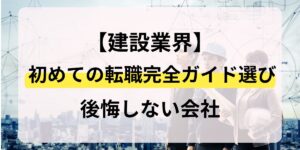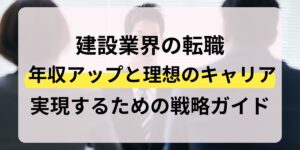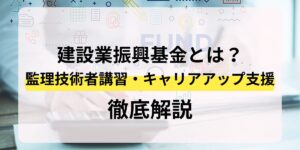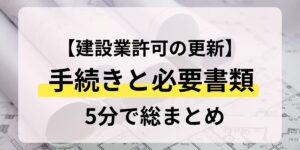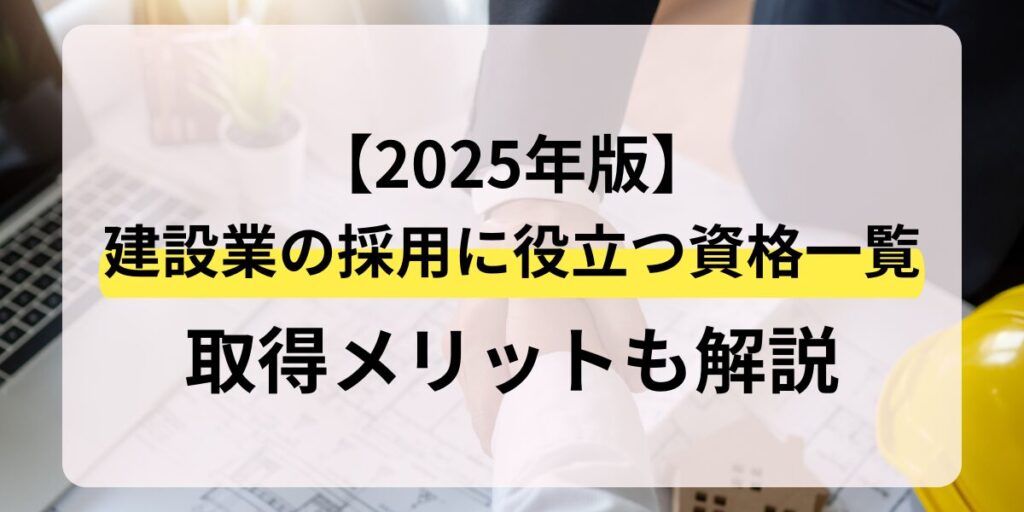
「優秀な人材を確保したいが、応募者のスキルをどう見極めれば良いか」「人手不足を解消し、企業の技術力を高めたい」。建設業界の採用担当者様なら、一度はこうした課題に直面したことがあるのではないでしょうか。その鍵を握るのが「資格」です。資格は、求職者のスキルを客観的に証明するだけでなく、企業の信頼性や受注機会にも直結します。
この記事では、採用で評価される主要な資格から、社員の資格取得を後押しするメリット、さらには外国人材の活用まで、企業の成長につながる資格戦略を分かりやすく解説します。
・採用で評価される、建設業界の主要な資格
・社員の資格取得を支援することのメリット
・外国人材の採用における資格の重要性
\ 建設業界の転職ならミライ建設ナビ /
建設業界で「資格」が重要視される3つの理由
建設業界において、なぜこれほどまでに資格が重要視されるのでしょうか。その背景には、大きく分けて3つの理由があります。
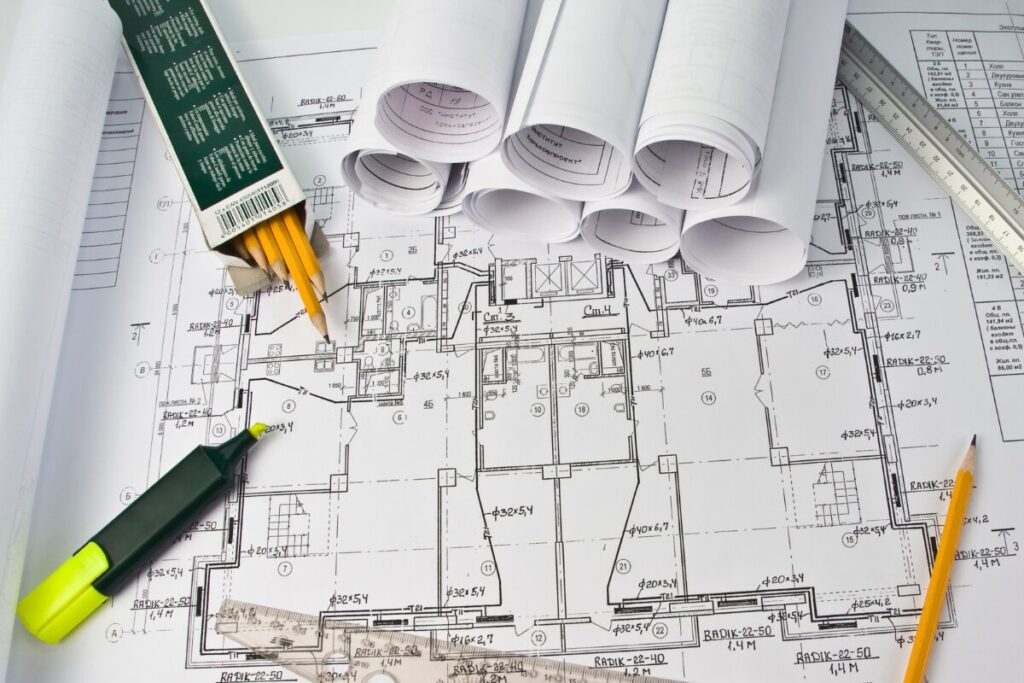
専門性の証明と企業の信頼性向上
建設工事は、人々の安全な暮らしを支える社会インフラを築く仕事です。ほんの少しのミスが、建物の耐久性や安全性に大きな影響を及ぼす可能性があります。
そのため、発注者(お客様)や取引先は、「確かな技術力と知識を持った会社に任せたい」と考えるのが自然です。資格は、国や公的機関が定めた基準をクリアした技術者であることの客観的な証明書となります。
資格保有者が多く在籍している企業は、それだけで「専門性の高いプロ集団」という印象を与え、顧客からの信頼獲得につながります。これは、企業のブランドイメージを向上させ、競合他社との差別化を図る上でも非常に重要な要素です。
法律で定められた技術者の必置義務
建設業法では、建設工事の適正な施工を確保するため、営業所ごと、また工事現場ごとに一定の資格や実務経験を持つ技術者を配置することが義務付けられています。これを「技術者の必置義務」と呼びます。
専任の技術者: 営業所に常勤し、請け負った工事の適正な契約や見積もり、施工を技術的な側面から支える役割を担います。
監理技術者・主任技術者: 工事現場に配置され、施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理など、現場全体のマネジメントを行います。特に大規模な工事では、監理技術者の配置が必須です。
これらの技術者がいなければ、企業は建設業の許可を維持したり、一定規模以上の工事を請け負ったりすることができません。つまり、資格保有者の確保は、事業を継続するための生命線とも言えるのです。
公共工事の入札で有利になる経営事項審査
国や地方自治体が発注する公共工事の入札に参加するためには、経営事項審査(経審)を受ける必要があります。
【ポイント】経営事項審査(けいえいじこうしんさ)とは?
公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。企業の経営状況、経営規模、技術力、社会性などを客観的な指標で点数化し、評価します。
この経審の評価点(総合評定値P)が高いほど、規模の大きな工事の入札で有利になります。そして、この点数を大きく左右するのが「技術力(Z点)」です。技術力は、在籍している技術者の資格の種類や人数によって評価されます。
【一覧】採用で評価される建設業の主要資格
建設業界には多種多様な資格が存在します。ここでは、特に採用市場で評価が高く、企業の技術力の中核となる主要な資格を4つのカテゴリーに分けて解説します。
施工管理系|現場全体の司令塔
施工管理技士は、工事現場における「4大管理(品質、工程、原価、安全)」を担う、まさに現場の司令塔です。これらの資格保有者は、企業の技術力の根幹を支える存在として極めて重要です。
建築施工管理技士
ビルやマンション、住宅、商業施設といった建築工事全般のスペシャリストです。設計図を基に、施工計画を立て、現場の職人をまとめながら、工事がスムーズかつ安全に進むよう全体を管理します。1級と2級があり、1級保有者は大規模な建築工事の監理技術者になることができます。
土木施工管理技士
道路、橋、トンネル、ダム、上下水道など、社会インフラの整備に不可欠な土木工事のプロフェッショナルです。自然環境への配慮や、災害に強いインフラづくりなど、建築工事とは異なる専門知識が求められます。こちらも1級と2級に分かれており、公共工事で非常に需要の高い資格です。
電気工事施工管理技士
建物の電気設備(照明、コンセント、受変電設備など)工事の施工管理を行います。現代の建物に電気は不可欠であり、その設置から管理までを担う専門家は常に求められています。オール電化やスマートホームの普及により、今後も重要性は増していく資格です。
管工事施工管理技士
空調設備、給排水設備、ガス配管など、建物内の「管」に関する工事を管理します。人々の快適な生活環境を維持するために欠かせない仕事であり、建物の省エネ化や衛生管理においても重要な役割を果たします。
【2025年最新情報】施工管理技士の受験資格が緩和されました!
- 2級(第二次):実務経験年数が一律 4年 に統一(鋼構造物塗装・薬液注入を除く)。
- 1級(第一次):19歳以上 なら実務経験を問わず受験可能に。
詳細は国土交通省の発表をご確認ください。 公式情報はこちら
設計・監理系|建物のスペシャリスト
建物の設計や、設計図通りに工事が行われているかをチェック(工事監理)する役割を担います。創造性と専門性が求められる仕事です。
建築士(一級・二級・木造)
建物の設計・工事監理を行うための国家資格です。資格の種類によって扱える建物の規模や構造、用途が異なります。
・一級建築士:扱える建物に制限がなく、高層ビルや大規模な商業施設など、あらゆる建物の設計・監理が可能です。最難関の資格であり、保有者は高く評価されます。
・二級建築士:戸建て住宅など、比較的小規模な建物の設計・監理を主に行います。地域に根差した工務店や設計事務所で中心的な役割を担います。
・木造建築士:木造建築物に特化した資格で、伝統的な工法や木材に関する深い知識が求められます。
建築設備士
空調・換気、給排水・衛生、電気など、建築「設備」の設計・工事監理に関する専門家です。建築士が設備の専門家である建築設備士にアドバイスを求め、共同で設計を進めることも多く、建物の快適性や省エネ性能を高める上で欠かせない存在です。
技術・作業系|専門技能のプロフェッショナル
現場で実際に手を動かし、専門的な作業を行うための資格です。これらの資格保有者がいることで、工事の品質と安全性が担保されます。
電気工事士
建物の電気設備の工事に従事するための国家資格。第一種と第二種があり、扱える電圧の範囲が異なります。この資格がなければ電気工事を行えない「業務独占資格」のため、非常に需要が高いです。
消防設備士
消火器やスプリンクラー、火災報知器などの消防用設備の設置工事や点検・整備を行います。人命に関わる重要な役割を担うため、建物には必ず必要な資格です。扱う設備によって甲種・乙種に分かれています。
建設機械施工技士
ブルドーザーやクレーン、ショベルカーといった建設機械の運転・操作、および施工管理を行うための資格です。現場の作業効率と安全性を両立させるために不可欠な専門家です。
不動産・その他|事業を多角的に支える資格
建設業は、建物を建てるだけでなく、土地の売買や経営管理も重要です。事業を多角的に支える資格も、企業の成長に貢献します。
宅地建物取引士(宅建士)
不動産の売買や賃貸の仲介において、重要事項の説明などを行うための国家資格です。自社で建築した建売住宅を販売したり、不動産事業を展開したりする建設会社にとって、必須の資格と言えます。
建設業経理士
建設業界特有の会計処理(未成工事支出金など)をマスターした、経理のスペシャリストです。正確な原価計算や経営分析は、企業の健全な経営に不可欠であり、経審においても評価される資格です。
企業が社員の資格取得を支援するメリット
社員に時間や費用をかけてまで資格を取らせることに、どんなメリットがあるのでしょうか。実は、資格取得支援は、企業にとって非常に効果の高い「投資」となります。
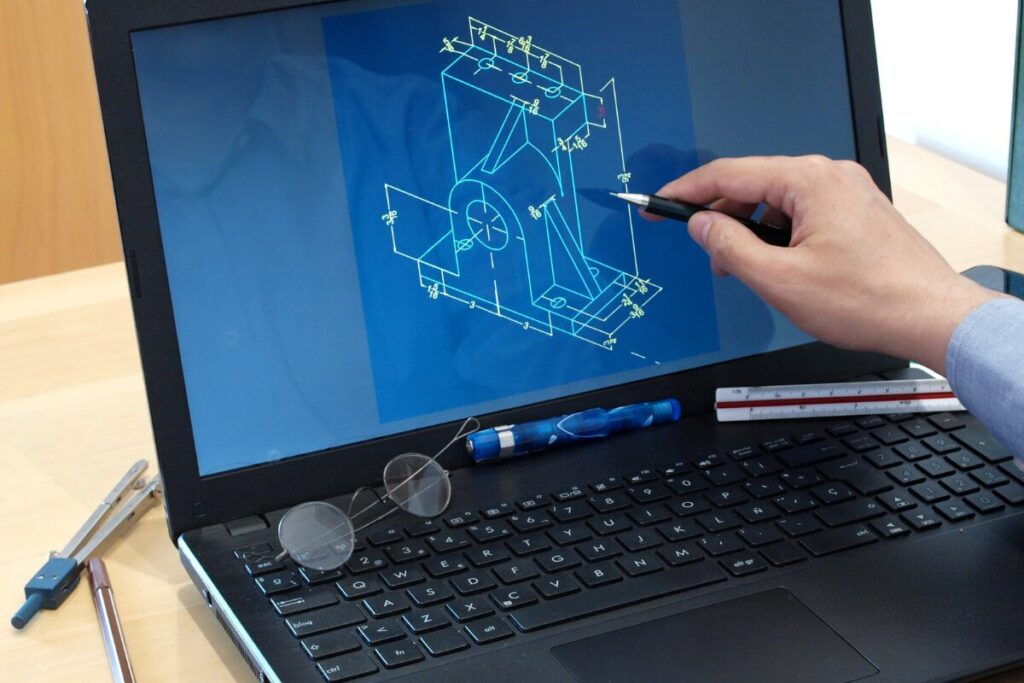
技術力の底上げと生産性の向上
社員が資格取得を目指して学習する過程で、最新の技術や法律、工法に関する知識を体系的にインプットすることになります。これまで経験則で何となく行っていた作業も、理論的な裏付けを持って取り組めるようになり、業務の質が格段に向上します。
・施工ミスの削減による手戻りの防止
・効率的な工程管理による工期の短縮
・新しい技術の導入による生産性の向上
こうした個々のレベルアップが組織全体に波及し、企業全体の技術力を底上げする力となります。
従業員の定着とモチベーションアップ
「この会社にいれば、スキルアップできる」「成長を応援してくれる」という実感は、従業員のエンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)を高める上で非常に重要です。
- 明確なキャリアパスの提示:資格取得を昇進・昇給の条件にすることで、社員は目標を持って仕事に取り組めます。
- 成長実感:難関資格に合格したという成功体験は、大きな自信と仕事への誇りにつながります。
- 経済的なインセンティブ:資格手当や報奨金は、学習への強力な動機付けとなります。
こうした取り組みは、社員の満足度を高め、優秀な人材の離職を防ぐ効果が期待できます。採用コストが年々高騰する中、既存社員の定着率を高めることは、経営戦略上も極めて重要です。
企業の評価と受注機会の拡大
前述の通り、有資格者の数は公共工事の入札(経営事項審査)で有利に働くだけでなく、民間工事においても企業の信頼性を測る指標となります。
・公式サイトや会社案内でのアピール:「1級建築士〇名、1級建築施工管理技士〇名 在籍」といった情報は、顧客に対する強力なアピール材料です。
・金融機関からの評価向上:技術力の高い企業は、事業の安定性・将来性が高いと判断され、融資審査などで有利になることがあります。
・リクルート効果:資格取得支援が手厚い企業は、スキルアップ志向の強い優秀な求職者にとって魅力的であり、採用競争においても優位に立てます。
戦略的に資格取得を推進することは、企業の社会的評価を高め、持続的な成長と受注機会の拡大に直結するのです。
社員の資格取得をサポートする具体的な方法
では、企業として具体的にどのようなサポートができるのでしょうか。ここでは、明日からでも始められる3つの方法を紹介します。

資格取得支援制度を導入する
最も効果的な方法の一つが、ルールとして明確な「資格取得支援制度」を設けることです。制度化することで、全社員が公平にサポートを受けられるようになり、利用促進にもつながります。
・受験費用の負担:1回目、もしくは合格した場合の受験費用を会社が全額または一部負担します。
・資格手当の支給:月々の給与に資格手当を上乗せします。資格の難易度に応じて金額に差をつけるのが一般的です。(例:1級建築士 3万円/月、2級建築施工管理技士 5千円/月)
・合格報奨金の支給:資格取得時に、一時金としてお祝い金を支給します。(例:1級土木施工管理技士 合格で10万円)
・学習時間の確保:試験前の休暇取得を認めたり、業務時間内での学習を一部許可したりします。
外部講習や通信講座の費用を補助する
特に難易度の高い資格は、独学だけで合格するのは容易ではありません。専門学校(スクール)や通信講座は、合格への近道となる強力なツールです。
企業がこれらの受講費用を全額または一部補助することで、社員は金銭的な負担を気にせず、質の高い学習に専念できます。法人契約を結ぶことで、個人で申し込むよりも安価に受講できるサービスも多いため、検討する価値は高いでしょう。
社内勉強会などで学習環境を整える
費用をかけずに人材を伸ばすには、勉強しやすい社内環境づくりが有効です。資格保有者が講師となる勉強会で試験の勘所や実体験を共有し、教える側の知識の再確認にも。会議室の就業後・休日開放で学習スペースを確保し、参考書・過去問の社内ライブラリー整備で学びを支援。小さな取り組みの継続が学び合う文化を育て、コミュニケーション活性化と組織の底上げ、資格取得率向上や離職抑制にもつながります。
【注目】外国人材と建設業の資格
深刻な人手不足が続く建設業界において、外国人材は今や欠かせない存在です。ここでは、外国人材の活躍と資格取得について解説します。

外国人材も取得できる日本の建設資格
日本の建設関連の国家資格の多くは、受験資格に国籍要件がありません。
つまり、建築士や施工管理技士といった難関資格も、必要な実務経験や学歴を満たせば、外国人材でも日本人と同様に受験し、取得することが可能です。
外国人社員に対して、日本人社員と変わらないキャリアアップの道筋を示すことは、彼らのモチベーションを高く維持し、長期的な定着を促す上で非常に重要です。資格取得を目標に設定することで、専門知識だけでなく、日本語能力の向上も期待できます。
即戦力にもなる「特定技能」と資格の関係
「特定技能」とは、国内人材の確保が困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れるための在留資格です。建設分野もこの対象となっています。
特定技能1号の在留資格を得るためには、「技能評価試験」と「日本語能力試験」の両方に合格する必要があります。この技能評価試験は、各職種(型枠施工、左官、鉄筋施工など)で求められる基本的な技能水準を満たしているかを測るものです。
つまり、「特定技能」の資格を持つ外国人は、入社時点である程度の専門スキルとコミュニケーション能力が担保された、まさに即戦力候補の人材なのです。
さらに、特定技能1号で経験を積んだ後、より高い技能レベルを証明する試験に合格し、一定の現場管理経験(班長など)を積むことで、在留期間の更新上限がなくなり、家族の帯同も可能になる「特定技能2号」へ移行できます。特定技能2号の技能水準は、主任技術者として認められるレベルに相当すると考えられており、まさに企業の技術力の中核を担う人材となり得ます。
外国人材を単なる労働力としてではなく、資格取得を通じて成長し、長く会社に貢献してくれるパートナーとして育成していく視点が、これからの建設業界では不可欠です。
まとめ:戦略的な資格取得で企業の未来を築く
この記事では、建設業界における資格の重要性から、主要な資格の種類、そして社員の資格取得を支援するメリットや具体的な方法までを網羅的に解説しました。
資格は、もはや単なる個人のスキル証明ではありません。
これからの時代を勝ち抜くためには、場当たり的な採用や育成ではなく、自社の事業戦略と連動した「資格取得戦略」を立て、計画的に人材育成へ投資していく視点が不可欠です。
この記事が、貴社の採用活動と人材育成の一助となれば幸いです。