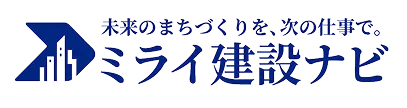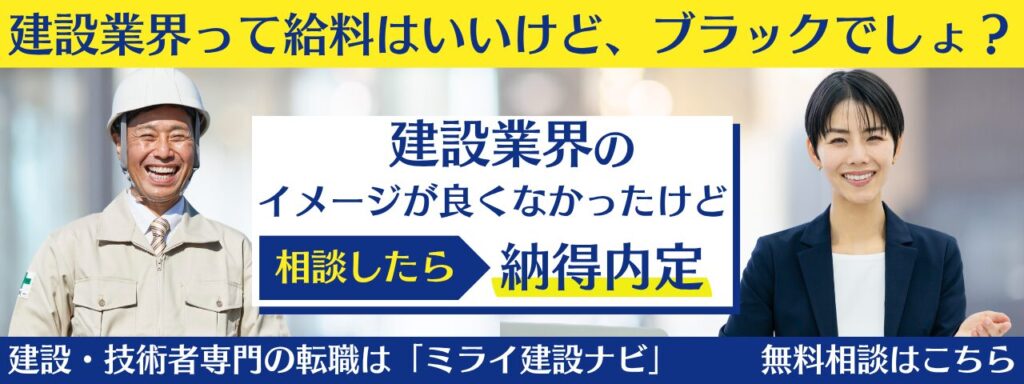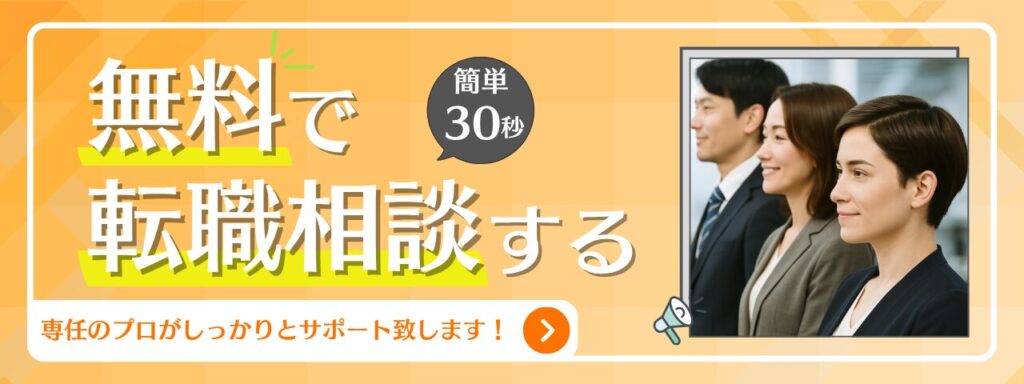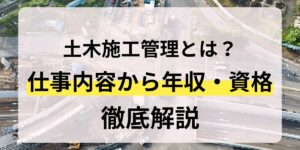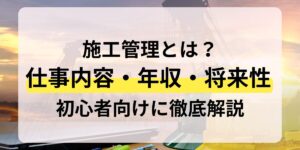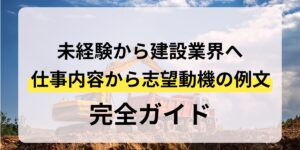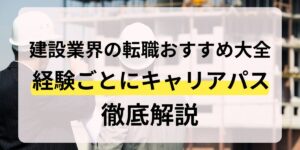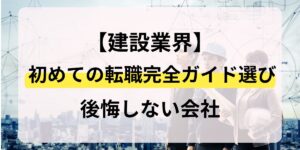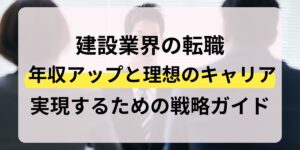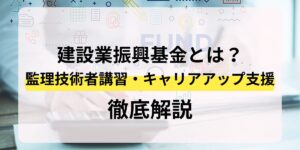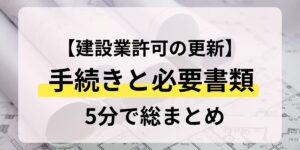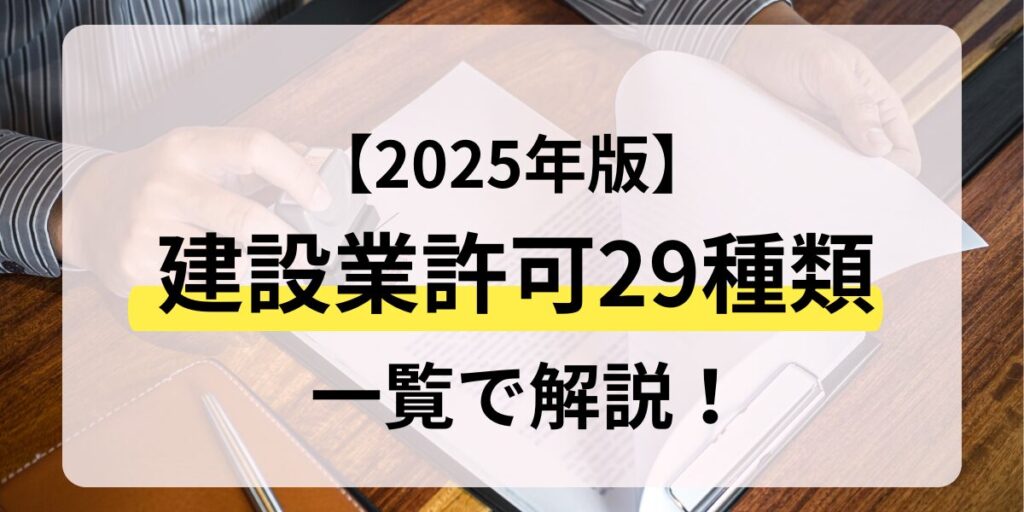
建設業を営む上で避けて通れない「建設業許可」。全29種類もあると聞き、どれが自社に必要なのか、そもそも違いが何なのか、お悩みではありませんか?
この記事では、複雑な建設業許可の種類を一覧でわかりやすく解説し、事業内容に合わせた許可の選び方までを具体的にご紹介します。許可取得を検討し、事業拡大と優秀な人材確保への第一歩を踏み出しましょう。この記事でわかる3つのポイント
・29種類ある建設業許可の全体像
・各業種ごとの具体的な工事内容や事例
・建設業許可が、企業の信頼性向上や採用活動
\ 建設業界の転職ならミライ建設ナビ /
そもそも建設業許可とは?
建設業許可とは、建設業法第3条に基づき、一定規模以上の建設工事を請け負うために必要となる許可のことです。この制度は、工事の品質を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促すことを目的としています。
許可なく大規模な工事を請け負うと、厳しい罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)が科される可能性があるため、建設業を営む事業者にとって極めて重要な制度です。
なぜ建設業許可が必要になるのか
すべての建設工事に許可が必要なわけではありません。建設業法では、比較的規模の小さい工事を「軽微な建設工事」と定め、これに該当する場合は許可がなくても請け負うことが可能です。
- 建築一式工事の場合
・1件の請負代金が1,500万円未満の工事
・請負代金にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事 - 建築一式工事以外の専門工事の場合
・1件の請負代金が500万円未満の工事
つまり、これを超える金額の工事を請け負う場合には、必ず建設業許可が必要になります。事業を拡大し、より大きな案件を受注していくためには、建設業許可の取得が不可欠なステップとなります。
「大臣許可」と「知事許可」の違い
建設業許可は、許可を与える行政庁(許可行政庁)によって「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」の2つに分かれます。これは、営業所の所在地によって決まります。
| 許可の種類 | 営業所の設置場所 |
| 国土交通大臣許可 | 2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合 |
| 都道府県知事許可 | 1つの都道府県のみに営業所を設置する場合 |
例えば、本社が東京にあり、大阪にも支店を設置して営業する場合は「大臣許可」が必要です。一方、大阪府内のみに複数の営業所を置く場合は「知事許可」となります。工事を行う場所が全国各地であっても、営業所が1つの都道府県内だけであれば「知事許可」で問題ありません。
「一般建設業」と「特定建設業」の違い
さらに、許可は「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類に区分されます。これは、元請けとして受注した工事を下請けに出す際の金額によって区別されます。
| 許可の種類 | 下請契約の金額(1件の工事につき) |
| 一般建設業許可 | 下請けに出す金額が合計4,500万円未満(建築一式工事は7,000万円未満)の場合 |
| 特定建設業許可 | 下請けに出す金額が合計4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の場合 |
・一般建設業許可:下請として工事を行う場合や、元請でも下請に出す金額が上記の範囲内であれば、こちらの許可で十分です。多くの事業者はまず一般建設業許可の取得を目指します。
・特定建設業許可:大規模な工事を元請として受注し、その多くを下請業者に発注する、いわゆるゼネコンなどが取得します。下請業者を保護する観点から、財産的要件や技術者要件が一般建設業許可よりも厳しく設定されています。
自社の事業形態が、元請中心か下請中心か、また将来的に大規模な元請工事を受注したいかによって、どちらの許可を取得すべきか判断します。
建設業許可の29種類を一覧で解説
建設業許可は、工事の種類に応じて2種類の一式工事と27種類の専門工事、合計29の業種に分類されています。どの業種の許可を取得するかは、自社が請け負う工事の内容と完全に一致している必要があります。
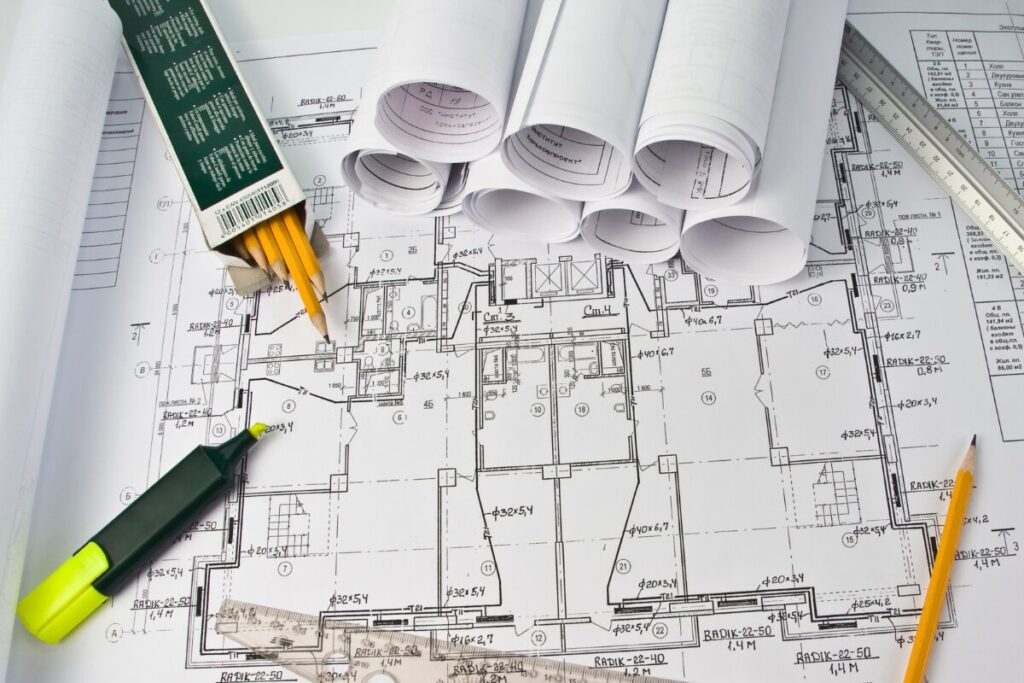
全ての工事を統括する「一式工事」(2種類)
一式工事は、大規模で複雑な工事を、企画、指導、調整しながら全体を完成させる役割を担います。元請業者が取得する代表的な許可です。
「土木一式」や「建築一式」の許可は、総合的な管理を行うための許可です。そのため、これらの許可を持っていても、500万円以上の専門工事(例:大工工事、電気工事など)を単独で請け負うことはできません。 専門工事を請け負うには、別途その専門工事の許可が必要です。
1,土木一式工事(土)
・概要:複数の専門工事(とび・土工、舗装、水道施設など)を組み合わせて、橋やダム、道路、上下水道といった土木工作物を建設する工事。
・工事例:道路工事、橋梁工事、ダム工事、河川工事、トンネル工事、上下水道配管工事
2,建築一式工事(建)
・概要:複数の専門工事(大工、内装、屋根、管など)を組み合わせて、家やビルなどの建築物を建設する工事。
・工事例:住宅新築工事、増改築工事、ビル建設工事、学校・病院の建設工事
専門分野を担当する「専門工事」(27種類)
専門工事は、一式工事以外の個別の専門的な工事を指します。全27種類を具体的に見ていきましょう。
- 大工工事(大)
- 木材の加工や取付けにより工作物を築造、または工作物に木製設備を取り付ける工事。
- 工事例:大工工事、型枠工事、造作工事
- 左官工事(左)
- 工作物の壁や床、天井などに、こてを使ってモルタルや漆喰などを塗り仕上げる工事。
- 工事例:左官塗り、モルタル工事、吹付け工事、とぎ出し工事
- とび・土工・コンクリート工事(と)
- 足場の組立て、重量物の運搬配置、土砂等の掘削や盛土、コンクリート打設など、非常に範囲の広い工事。
- 工事例:足場組立、鉄骨組立、杭打ち、掘削工事、コンクリート工事、工作物解体工事(※解体工事の専門許可が新設)
- 石工事(石)
- 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工または積方により工作物を築造、または工作物に石材を取り付ける工事。
- 工事例:石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
- 屋根工事(屋)
- 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事。
- 工事例:瓦ぶき工事、スレートぶき工事、金属製屋根工事、屋根断熱工事
- 電気工事(電)
- 発電設備、変電設備、送配電線、構内電気設備等を設置する工事。
- 工事例:発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、照明設備工事、信号設備工事
- 管工事(管)
- 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事。
- 工事例:冷暖房設備工事、給排水・給湯設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事
- タイル・れんが・ブロック工事(タ)
- れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、または張り付ける工事。
- 工事例:コンクリートブロック積み(張り)工事、タイル張り工事、ALCパネル工事
- 鋼構造物工事(鋼)
- 形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事。
- 工事例:鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、屋外広告工事
- 鉄筋工事(筋)
- 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組立てる工事。
- 工事例:鉄筋加工組立工事、鉄筋継手工事
- 舗装工事(舗)
- 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事。
- 工事例:アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事
- しゅんせつ工事(しゅ)
- 河川、港湾等の水底の土砂などを掘り下げて取り除く工事。
- 工事例:河川・港湾の浚渫工事
- 板金工事(板)
- 金属薄板等を加工して工作物に取り付け、または工作物に金属製等の付属物を取り付ける工事。
- 工事例:建築板金工事、ダクトの製作・取付、厨房のステンレス加工工事
- ガラス工事(ガ)
- 工作物にガラスを加工して取り付ける工事。
- 工事例:窓ガラス工事、ガラスフィルム工事、ショーウインドウ工事
- 塗装工事(塗)
- 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、または張り付ける工事。
- 工事例:建築塗装、橋梁塗装、溶射工事、ライニング工事
- 防水工事(防)
- アスファルト、モルタル、シーリング材等によって水の浸入を防ぐ工事。
- 工事例:アスファルト防水工事、シーリング工事、ウレタン防水工事、シート防水工事
- 内装仕上工事(内)
- 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事。
- 工事例:インテリア工事、天井仕上工事、床仕上工事、クロス工事、間仕切り工事
- 機械器具設置工事(機)
- 機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取り付ける工事。個別の機械の設置ではなく、プラント設備のような現場での組立てが必要な大規模なものが該当する。
- 工事例:プラント設備工事、エレベーター・エスカレーター設置工事、立体駐車場設備工事
- 熱絶縁工事(絶)
- 工作物または工作物の設備を熱の遮断・保温・保冷のために施工する工事。
- 工事例:冷暖房設備や冷凍冷蔵設備の配管・ダクトの保温・保冷工事
- 電気通信工事(通)
- 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事。
- 工事例:電話設備工事、LAN設備工事、テレビ電波障害防除設備工事、防犯カメラ設置工事
- 造園工事(園)
- 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事。
- 工事例:植栽工事、地被工事、景石工事、公園設備工事、屋上緑化工事
- さく井工事(さ)
- さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事、またはこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事。
- 工事例:井戸掘り工事、温泉掘削工事、観測井工事
- 建具工事(具)
- 工作物に木製または金属製の建具等を取り付ける工事。
- 工事例:サッシ取付工事、シャッター取付工事、ドア取付工事、ふすま工事
- 水道施設工事(水)
- 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事、または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事。
- 工事例:取水施設工事、浄水施設工事、配水管布設工事、下水処理場施設工事
- 消防施設工事(消)
- 火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取り付ける工事。
- 工事例:屋内・屋外消火栓設置工事、スプリンクラー設備工事、火災報知設備工事
- 清掃施設工事(清)
- し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事。
- 工事例:ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
- 解体工事(解)
- 工作物を取り壊す工事。以前は「とび・土工・コンクリート工事」に含まれていたが、専門性が高いため独立した。
- 工事例:建物解体工事、工作物解体工事
どの許可を取るべき?業種選び3つのポイント
29種類の中から自社に必要な許可を正確に選ぶことは、事業の将来を左右する重要な判断です。以下の3つのポイントを参考に、検討を進めてください。
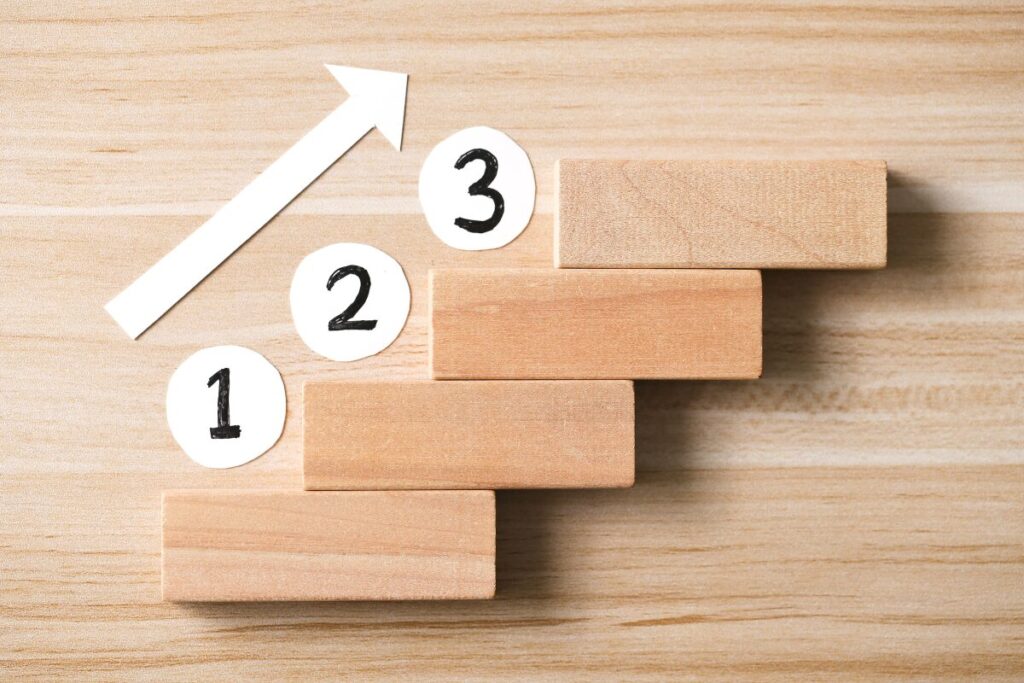
①現在の主力事業から判断する
まずは自社の「現在」を見つめ直しましょう。
過去数年間の工事実績や、売上の大部分を占めている工事は何かを洗い出します。その工事が29業種のどれに該当するかを確認するのが基本です。例えば、住宅の壁紙や床の張り替えをメインに行っているなら「内装仕上工事」、商業施設の空調ダクト設置が主なら「管工事」の許可が必要になります。
発注書や契約書を見返し、工事内容を正確に把握することが第一歩です。
②将来の事業展開から検討する
次に、自社の「未来」を考えます。
「現在は内装工事が中心だが、今後はリフォーム全般を手掛け、水回り(管工事)や電気(電気工事)も自社で一括受注したい」というビジョンがあるなら、将来を見据えて関連する業種の許可取得を計画することが重要です。
5年後、10年後にどのような会社でありたいか、どんな工事を請け負っていたいかを具体的に描くことで、今取得すべき許可、将来的に追加すべき許可が見えてきます。
③複数の業種許可を同時に取得する
建設工事は、複数の専門分野にまたがることが少なくありません。例えば、キッチンリフォームでは「内装仕上工事」の他に「管工事」や「電気工事」が伴います。
こうした関連性の高い業種の許可を複数取得しておくことで、受注できる工事の幅が格段に広がります。
「この部分は対応できないので、他社にお願いしてください」となると、受注機会の損失(機会損失)に繋がります。ワンストップで対応できる体制は、発注者からの信頼を高め、企業の競争力強化に直結します。申請は同時に行うことも可能なので、事業内容に合わせてまとめて取得を検討しましょう。
建設業許可が採用活動に与える好影響
建設業許可の取得は、単に大規模な工事を請け負えるようになるだけではありません。企業の信頼性を高め、採用活動においても大きなメリットをもたらします。

公共工事への参加で企業の信頼性アップ
建設業許可は、国や地方自治体が発注する公共工事の入札に参加するための必須条件です。公共工事の実績は、企業の技術力や経営の安定性を示す客観的な証明となり、金融機関からの融資や、民間企業との取引においても有利に働きます。
求職者にとっても、「公共工事を元請けで受注している」「コンプライアンス意識が高い」という事実は、安定した経営基盤を持つ企業として魅力的に映り、応募を集める上での強力なアピールポイントとなります。
求人サイトや採用面接でのアピール方法
取得した建設業許可は、採用活動の場で積極的にアピールしましょう。
・求人票の「応募資格」や「企業情報」欄に明記
例:「建設業許可(〇〇県知事許可(般-XX)第XXXXX号)」
・採用サイトで許可証の画像や取得業種を掲載
「内装・管・電気工事の許可を保有し、リフォームをワンストップで提供できる技術力があります」と具体的に訴求。
・面接で今後の事業展開とともに説明
「今後は特定建設業の許可も取得し、さらに大規模な公共工事にも挑戦していきます」と伝えることで、求職者に入社後のキャリアパスや会社の成長性をイメージさせることができます。
まとめ:建設業許可は事業成長と人材確保の土台
この記事では、建設業許可の基本的な仕組みから、複雑な29の業種区分、そして業種選びのポイントまでを解説しました。
建設業許可の取得は、500万円以上の工事を請け負うために不可欠なだけでなく、企業の社会的信用を高め、公共工事への道を開き、ひいては優秀な人材を惹きつけるための重要な経営戦略です。
自社の現在地を確認し、未来のビジョンを描きながら、事業に最適な許可を取得することが、持続的な成長の揺るぎない土台となります。