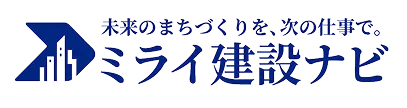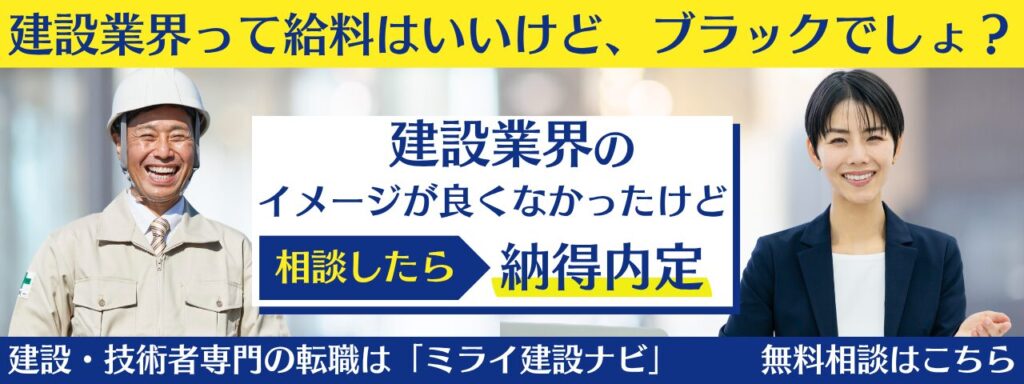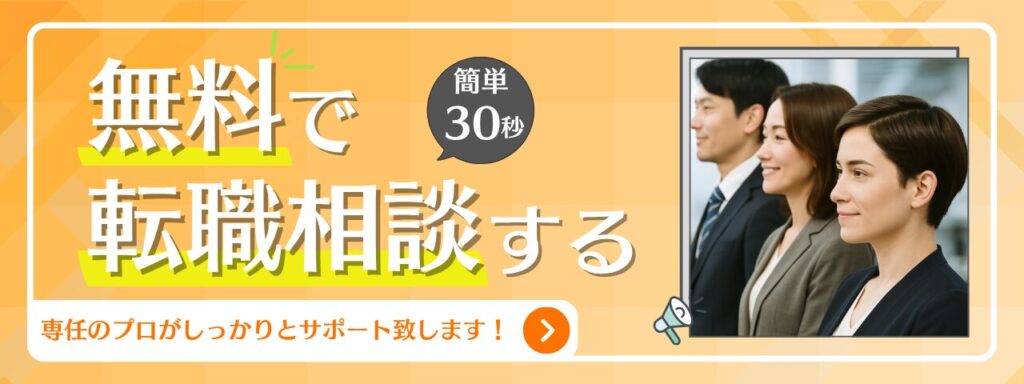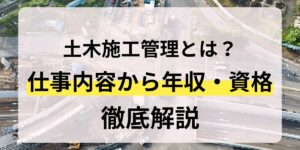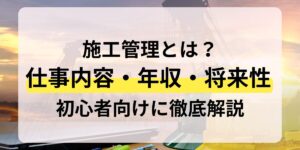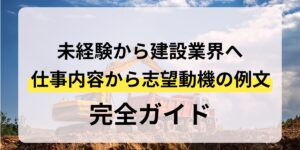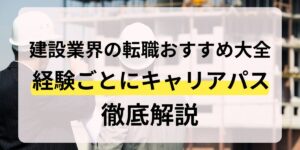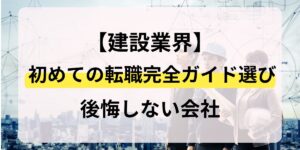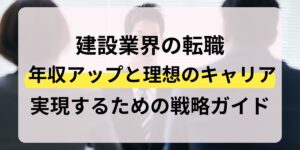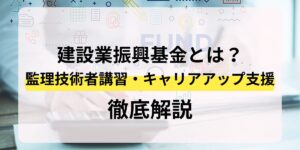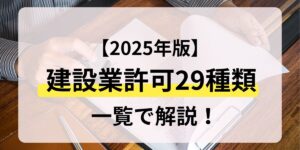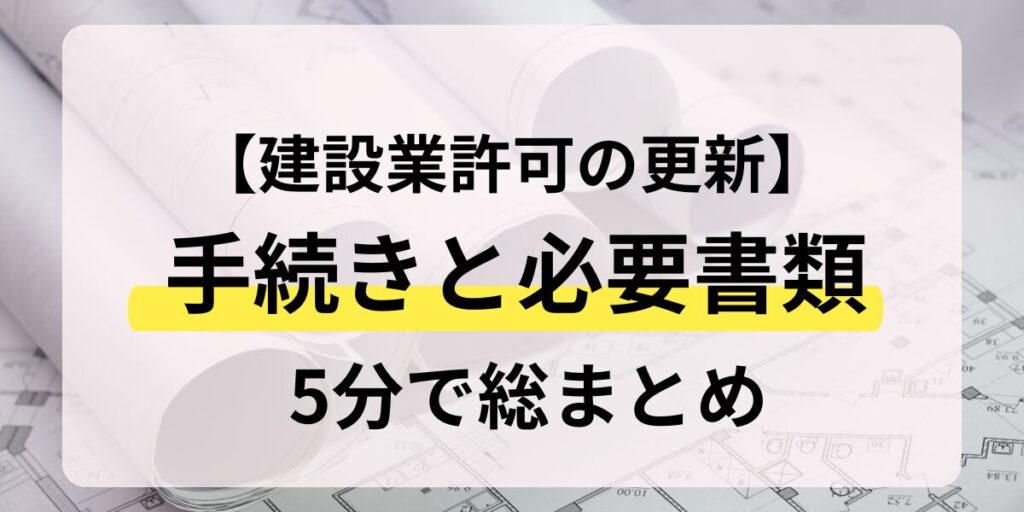
5年に一度の建設業許可の更新。日常業務に追われ、「まだ先のこと」と考えているうちに、気づけば期限が迫っていた、という経験はありませんか?
担当者が変わったばかりで手順がわからず、不安を感じている方もいるかもしれません。
この記事では、建設業許可の更新で失敗しないために、申請期間や必要書類、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。スムーズな手続きで、事業の信頼性を維持しましょう。この記事でわかる3つのポイント!
・建設業許可の更新手続き
・更新に必要な書類と、満たしておくべき要件
・更新をスムーズに進めるための注意点や費用
\ 建設業界の転職ならミライ建設ナビ /
建設業許可には5年の有効期間がある
まず、建設業許可の基本として、その有効期間を正確に理解しておくことが重要です。許可は一度取得すれば永続するものではなく、定期的な更新が法律で定められています。
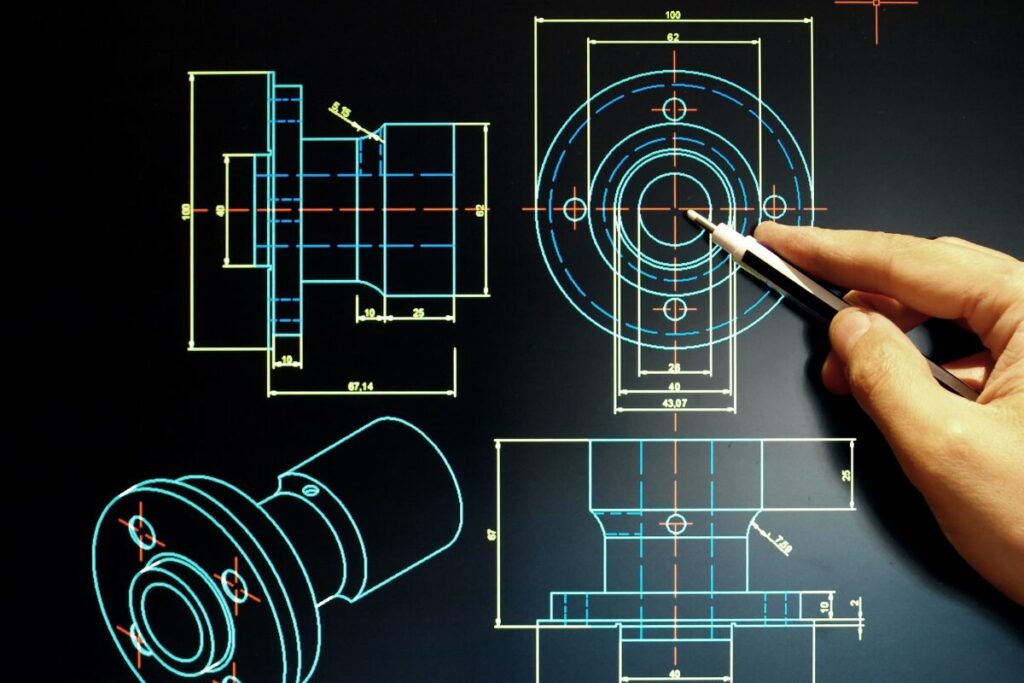
更新を忘れると許可は失効する
建設業許可の有効期間は、許可があった日から5年間です。具体的には、許可日の5年後の同日の前日をもって満了となります。
例えば、2025年10月1日に許可が下りた場合、有効期間の満了日は2030年9月30日です。この日までに更新手続きを完了させないと、許可は自動的に失効してしまいます。
うっかり更新を忘れてしまうと、再度許可を取得するためには「新規」での申請となり、許可がない期間が生じてしまいます。これは事業運営において大きなリスクとなります。
許可が切れると500万円以上の工事が不可に
建設業許可が失効すると、どのような影響があるのでしょうか。建設業法では、以下の「軽微な工事」を除き、建設工事の請負には建設業許可が必要と定められています。
・建築一式工事の場合: 請負代金が1,500万円未満(消費税込)の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
・建築一式工事以外の場合: 請負代金が500万円未満(消費税込)の工事
つまり、許可が切れた状態では、税込み500万円以上の工事(建築一式の場合は1,500万円以上)を請け負うことが一切できなくなります。
進行中の工事がある場合はもちろん、新たな契約もできなくなるため、事業の継続に深刻な影響を及ぼします。公共工事の入札参加資格も失うことになり、企業の信頼性も大きく損なわれます。
建設業許可の更新申請はいつまで?
更新手続きには申請期間が定められています。この期間を逃さないことが、許可を維持する上で最初の関門です。

H3: 有効期間満了日の30日前が原則
建設業許可の更新申請は、原則として有効期間が満了する日の30日前までに行う必要があります。
これは、申請を受けた行政庁(都道府県や地方整備局)が、審査に要する標準的な期間を考慮しているためです。申請から許可通知が下りるまでには一定の時間がかかるため、余裕を持った申請が求められます。
都道府県ごとに異なる申請期間
注意が必要なのは、上記の「30日前まで」はあくまで法律上の原則であり、実際の手続きでは、都道府県知事許可の場合、自治体ごとに独自の申請期間を設けているケースが多い点です。
・東京都・大阪府: 有効期間満了日の2ヶ月前まで
・神奈川県・埼玉県: 有効期間満了日の3ヶ月前まで
・愛知県: 有効期間満了日の30日前まで(原則通り)
このように、自治体によって2〜3ヶ月前を期限としている場合があるため、「30日前で大丈夫」と考えていると、受付を断られてしまう可能性があります。
必ず、自社の許可を管轄する都道府県のウェブサイトや担当窓口で、最新の申請期間を確認してください。 準備期間も考慮し、満了日の半年前には一度確認のアクションを取ることをお勧めします。
更新前にチェック!満たすべき5つの許可要件
更新申請をするには、新規で許可を取得した際と同様に、建設業法で定められた5つの要件をすべて満たしている必要があります。更新のタイミングで改めて自社の体制を確認しましょう。
適切な経営体制が維持されているか
法人の役員や個人事業主本人に、適切な経営能力があることが求められます。具体的には、常勤役員等(旧:経営業務の管理責任者)が下記のいずれかの経験を有し、社内に常勤している必要があります。
・許可を受けたい業種で、5年以上の経営経験
・許可を受けたい業種以外で、6年以上の経営経験
・経営業務を補佐した経験が6年以上 など
役員の退任や交代があった場合、後任者がこの要件を満たしているか、事前に確認が必須です。
社会保険に正しく加入しているか
建設業許可の要件として、社会保険(健康保険・厚生年金保険)および労働保険(雇用保険)への適切な加入が義務付けられています。
更新申請時には、社会保険の加入状況を証明する書類の提出が求められます。未加入の状態では、指導を受けるだけでなく、更新が認められません。従業員の雇用形態に応じて、適切な加入手続きが済んでいるか必ず確認してください。
専任技術者が常勤しているか
許可を受ける業種ごとに、専門知識や経験を持つ「専任技術者」を各営業所に常勤で配置しなければなりません。専任技術者になるための要件は、主に以下の通りです。
・国家資格を保有している: 1級・2級の建築施工管理技士、第一種電気工事士など、業種に応じた資格
・一定の学歴+実務経験がある: 指定学科(土木工学、建築学など)を卒業後、大卒なら3年、高卒なら5年以上の実務経験
・10年以上の実務経験がある: 資格や学歴がない場合でも、許可業種に関して10年以上の実務経験があれば認められます。
退職などで専任技術者が不在になった場合は、速やかに後任者を見つけ、変更届を提出する必要があります。
財産的・金銭的な信用があるか
請負契約を誠実に履行できるだけの財産的基礎があることも要件です。これは、許可の種類によって基準が異なります。
- 一般建設業許可の場合(下記のいずれかを満たすこと)
- 自己資本の額が500万円以上
- 500万円以上の資金を調達する能力がある(金融機関の預金残高証明書などで証明)
- 特定建設業許可の場合(下記のすべてを満たすこと)
- 欠損の額が資本金の20%を超えない
- 流動比率が75%以上
- 資本金の額が2,000万円以上
- 自己資本の額が4,000万円以上
これらの基準は、更新申請の直前の決算において満たしている必要があります。決算内容によっては更新ができない可能性もあるため、注意が必要です。
欠格要件に該当していないか
法人の役員や個人事業主、令で定める使用人などが、下記の欠格要件に該当しないことが求められます。
- 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
- 不正な手段で許可を取得したことなどにより、許可を取り消されてから5年を経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 など
これらの要件は、建設工事の請負契約に関する「誠実性」を担保するためのものです。
建設業許可の更新に必要な書類一覧
更新申請には多くの書類が必要です。不備なく揃えるために、早めに準備を始めましょう。ここでは代表的な書類を挙げますが、最終的には必ず管轄の行政庁が発行する「申請の手引き」をご確認ください。

申請書など作成が必要な書類
建設業許可:提出書類チェックリスト
-
建設業許可申請書様式第一号
-
役員等の一覧表様式第一号 別紙一
-
営業所一覧表様式第一号 別紙二
-
専任技術者証明書様式第八号
-
工事経歴書様式第二号
補足
申請直前の事業年度 1年分 を記載。
-
直前3年の各事業年度における工事施工金額様式第三号
-
財務諸表様式第十五号〜第十九号法人:貸借対照表・損益計算書 等/個人:貸借対照表・損益計算書
-
誓約書様式第六号
-
健康保険等の加入状況様式第二十号の三
これらの書類は、行政庁のウェブサイトから最新の様式(フォーマット)をダウンロードして作成します。
納税証明書など収集が必要な書類
建設業許可:追加提出書類チェックリスト
-
営業所の確認資料営業所の写真(外観・入口・内部)や賃貸借契約書の写し等
-
常勤役員等の確認資料住民票や健康保険被保険者証の写し等
-
専任技術者の確認資料住民票、資格者証の写し、健康保険被保険者証の写し等
-
法人事業税の納税証明書管轄の都道府県税事務所で取得
-
消費税及び地方消費税の納税証明書管轄の税務署で取得(その1:納税額等証明用)
-
登記事項証明書(法人の場合)
-
身分証明書(個人の場合)
証明書類は発行から3ヶ月以内といった有効期限が定められているものがほとんどです。取得するタイミングにも注意しましょう。
建設業許可の更新にかかる費用
更新手続きには、法定費用と、専門家に依頼する場合の報酬がかかります。
法定費用(印紙代)は5万円
建設業許可の更新申請には、一律50,000円の法定費用がかかります。これは、許可の種類(一般/特定、知事/大臣)にかかわらず同額です。
この費用は、申請書に収入印紙(大臣許可)または収入証紙(知事許可)を貼り付けて納付します。
行政書士に依頼する場合の報酬相場
更新手続きは複雑で時間もかかるため、行政書士などの専門家に代行を依頼する企業も多くあります。その場合の報酬は、事務所や依頼内容によって異なりますが、一般的には5万円〜10万円程度が相場です。
自社で手続きを行う時間や人件費、申請の確実性を考慮すると、専門家への依頼は有効な選択肢の一つです。特に、役員変更や決算変更届の未提出など、複雑な事情がある場合は相談してみる価値があるでしょう。
失敗しない!建設業許可更新の3つの注意点
更新手続きでつまずきやすい、特に重要な3つのポイントを解説します。これらを怠ると、更新申請が受理されない、あるいは手続きが大幅に遅れる原因になります。
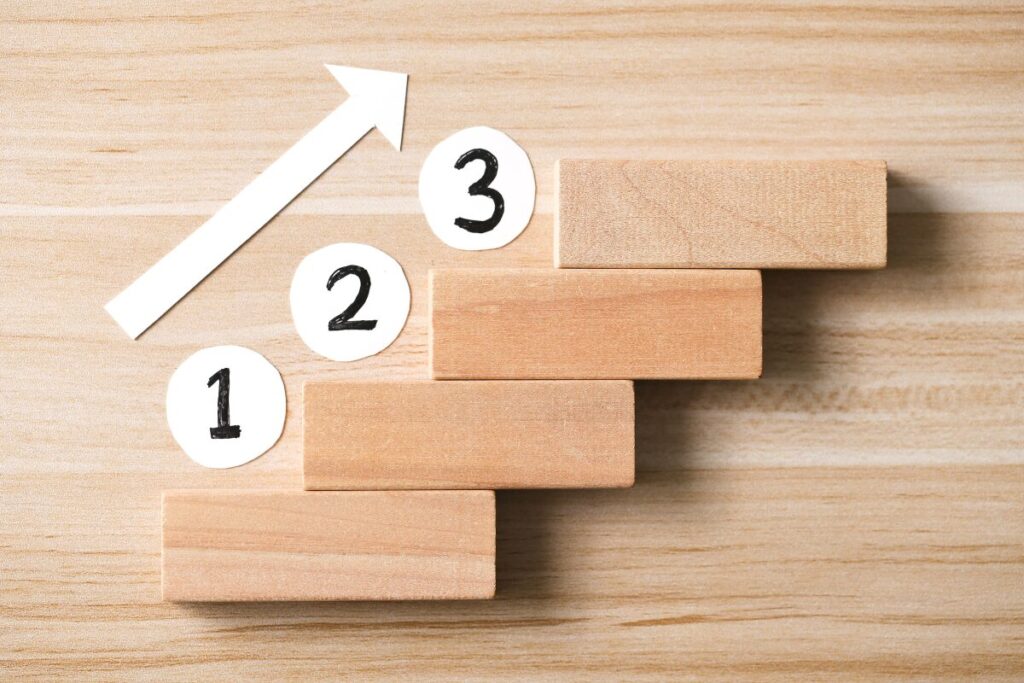
毎年の決算変更届を提出しているか
建設業許可業者は、事業年度が終了してから4ヶ月以内に「決算変更届(事業年度終了報告書)」を毎年提出する義務があります。この届出には、その年度の工事経歴書や財務諸表などが含まれます。
更新申請の際には、前回の許可(または更新)から今回の更新申請までの5年分の決算変更届がすべて提出済みであることが前提となります。もし未提出の年度があれば、まずその届出をすべて済ませないと、更新申請は受理されません。
溜めてしまった分の書類作成は大変な作業になるため、必ず毎年忘れずに提出しましょう。
役員や所在地の変更届は提出済みか
決算変更届と同様に、許可内容に変更があった場合は、その都度「変更届」を提出する必要があります。
【変更後30日以内に届出が必要な事項】
- 商号または名称
- 営業所の名称、所在地
- 資本金額
- 役員の氏名(新任・退任・氏名変更)
- 経営業務の管理責任者、専任技術者の交代・氏名変更 など
【変更後2週間以内に届出が必要な事項】
- 経営業務の管理責任者、専任技術者の要件を欠いた場合
これらの変更届を提出していないと、登記簿上の情報と許可情報に食い違いが生じ、更新手続きがスムーズに進みません。更新時にまとめて変更届を提出することも可能ですが、余計な手間と時間がかかります。変更があった際は、速やかに手続きを行いましょう。
複数の許可は有効期間を一本化できる
例えば、「東京都知事許可の内装仕上工事業」と「神奈川県知事許可の塗装工事業」を持っている場合や、「建築工事業」の許可取得後に「とび・土工工事業」を追加した場合など、許可の有効期間が複数存在することがあります。
この場合、それぞれの満了日にあわせて更新手続きが必要になり、管理が煩雑です。
そこで、「許可の有効期間の一本化」という手続きを行うことで、更新のタイミングを一つにまとめることができます。最も早く満了日を迎える許可の更新申請時に、他の許可もまとめて更新手続きを行うことで、次回以降の更新管理が非常に楽になります。該当する企業は、更新のタイミングで一本化を検討することをお勧めします。
よくある質問(Q&A)
最後に、建設業許可の更新に関するよくある質問にお答えします。
更新期限が切れたらどうなる?
A. 更新はできず、「新規」で許可を取り直す必要があります。
一度有効期間が切れてしまうと、いかなる理由があっても更新は認められません。許可を再度取得するには、新規申請と同じ手続き、書類、審査が必要になります。その間は無許可状態となり、500万円以上の工事は請け負えません。
また、許可番号も新しくなるため、過去の実績との継続性が途切れ、対外的な信用にも影響する可能性があります。
更新と同時に業種追加はできる?
A. はい、可能です。
更新のタイミングで、新たに別の業種の許可を取得したい(業種追加)場合は、更新申請と業種追加の新規申請を同時に行うことができます。
この場合、手数料は更新申請の5万円に加えて、業種追加の新規申請手数料5万円がかかります。書類もそれぞれ必要になりますが、同時に申請することで手続きの手間を一部省略できるメリットがあります。
まとめ:建設業許可の更新は、企業の信頼を守るための重要手続き
この記事では、5年に一度の建設業許可の更新について、申請期間から必要要件、注意点までを網羅的に解説しました。
これらのポイントを押さえ、計画的に準備を進めることが、スムーズな更新の鍵です。建設業許可を維持することは、法令遵守はもちろん、顧客や取引先からの信頼を確保し、安定した事業を継続していくための生命線と言えます。