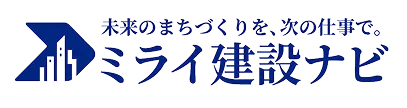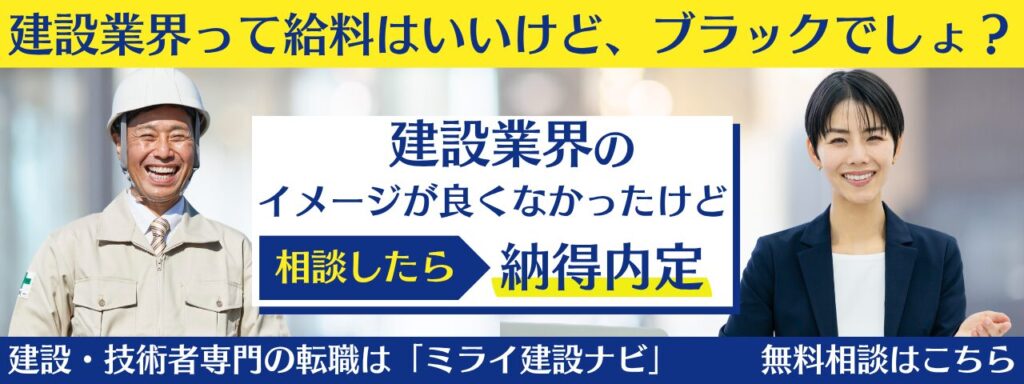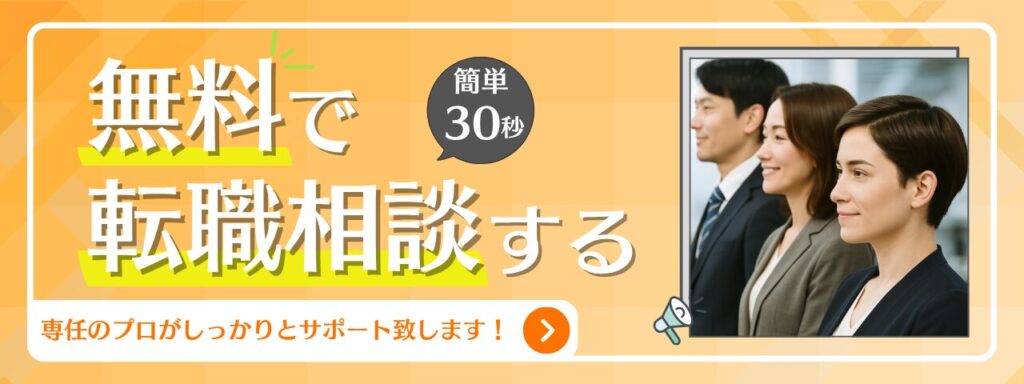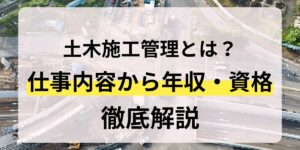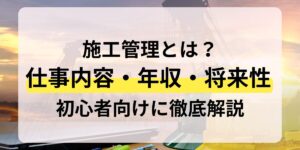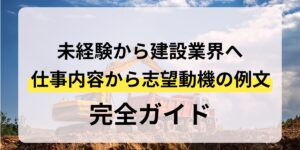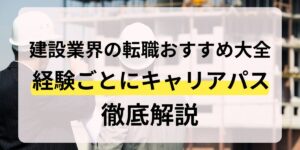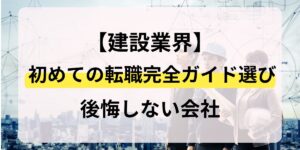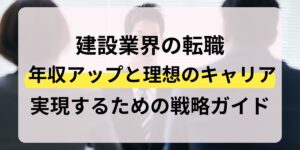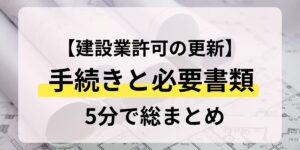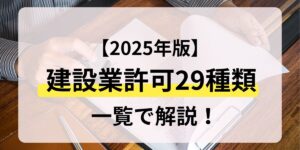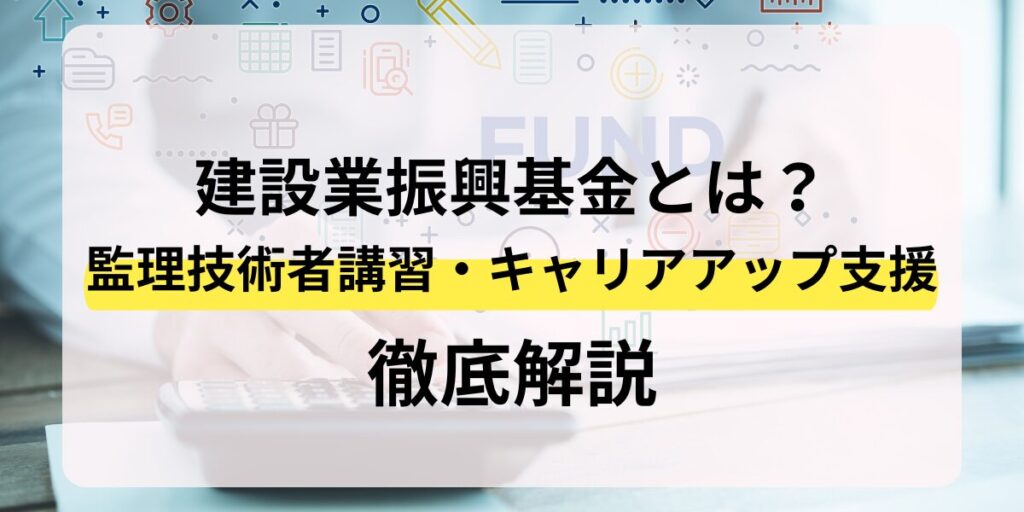
建設業界は、日本の社会インフラを支える基幹産業ですが、同時に「担い手不足」「技術者の高齢化」「生産性の向上」といった多くの課題を抱えています。これらの課題解決に向けて、官民一体でさまざまな取り組みが進められていますが、その中心的な役割を担う機関の一つが「建設業振興基金」です。
「名前は聞いたことがあるが、具体的に何をしている組織なのかよく知らない」「自社にとってどんなメリットがあるのか分からない」と感じている採用担当者や経営者の方も多いのではないでしょうか。
本記事では、建設業振興基金の基本から、企業が活用できる監理技術者講習、助成金制度、採用力強化に繋がるポイントまで、2025年最新の情報をもとに、分かりやすく徹底解説します。この記事を読むことで得られる3つのポイント
・建設業振興基金が建設業界で果たす役割
・監理技術者講習や助成金など、企業が活用
・建設キャリアアップシステム(CCUS)との連携
\ 建設業界の転職ならミライ建設ナビ /
建設業振興基金とは?
建設業振興基金(一般財団法人建設業振興基金)は、建設業法第25条の27に基づき、1975年(昭和50年)に設立された国土交通省所管の公益法人です。その名の通り、建設業の振興を目的としており、その活動は多岐にわたります。
設立の背景には、建設投資の安定的な確保や、建設業界の近代化・合理化を促進する必要性がありました。単なる営利団体ではなく、業界全体の健全な発展と、建設工事の品質確保という公的な使命を帯びています。
主な事業の柱は以下の4つです。
- 建設業の担い手の確保・育成支援:技術者や技能者の能力向上、若年層の入職促進
- 建設業の経営基盤の強化支援:経営力向上に関する調査研究や情報提供
- 建設生産システムの合理化・効率化:建設キャリアアップシステム(CCUS)の運営支援など
- 資金造成・助成事業:資格取得や人材育成に対する経済的支援
建設業振興基金は、法律に基づいて設立された公的な性格を持つ団体です。そのため、提供される情報や講習は信頼性が高く、その活動は業界標準として広く認知されています。企業にとっては、人材育成や経営改善を進める上での信頼できるパートナーと言えます。
建設業振興基金が実施する資格・講習・合格発表情報
建設業振興基金は、建設業界で働く人々のキャリア形成に不可欠な事業を数多く展開しています。ここでは、企業の採用・育成担当者が必ず押さえておくべき3つの主要な事業を詳しく解説します。

監理技術者講習
監理技術者は、特定建設業者が元請として受注した大規模工事(下請契約額の総額が4,500万円以上、建築一式工事は7,000万円以上)に必置とされる、極めて重要な役割を担う技術者です。
この監理技術者として業務を行うためには、有効期間内(5年間)の「監理技術者資格者証」と「監理技術者講習修了証(ラベル)」の両方が必要です。講習は、資格者証の有効期間を更新するために必須の手続きとなります。
建設技術や関連法規は、日々進化・改正されています。5年ごとの講習受講を義務付けることで、監理技術者が常に最新の知識・技術を習得し、工事の品質と安全を確保することを目的としています。講習では主に以下の内容を学びます。
- 建設工事に関する法律や制度の改正点
- 最新の建設技術や工法、建設資材に関する動向
- 建設工事の安全・品質管理に関する重要事項や事故事例
講習の種類と選び方
講習は、従来の「会場開催(対面講習)」に加え、近年では「オンライン講習」も普及しています。
| 形式 | メリット | デメリット |
| 会場開催 | ・講師に直接質問できる ・他の受講者との交流機会がある | ・開催地までの移動時間と交通費がかかる ・日程が固定されている |
| オンライン | ・場所や時間を選ばずに受講できる ・移動コストがかからない ・自分のペースで学習を進めやすい | ・自己管理能力が求められる ・インターネット環境が必須 |
企業の担当者としては、社員のスケジュールや希望、コストを考慮して最適な形式を選択・推奨することが求められます。
施工管理技士試験(合格発表スケジュール)
1級・2級施工管理技士は、建設業許可の要件である「営業所の専任技術者」や「工事現場の主任技術者・監理技術者」となるための重要な国家資格です。この資格保有者の数は、企業の技術力や受注能力に直結します。
施工管理技士試験の試験実施機関は「一般財団法人建設業技術者センター」ですが、建設業振興基金は、業界全体の情報ハブとして、試験日程や合格発表に関する情報を広くアナウンスする役割を担っています。
採用担当者は、これらのスケジュールを正確に把握し、戦略的に活用することが重要です。
【合格発表スケジュールの活用例】
資格試験の合格発表スケジュールは、採用・人事活動や組織運営にも有効活用できます。例えば、内定者フォローでは、受験予定者の合格発表日に合わせて激励の連絡を行い、入社意欲を高められます。社員のモチベーション管理では、合格発表日を社内で共有し、合格者を称賛することで資格取得を奨励する雰囲気を醸成できます。
さらに、次年度の採用計画では、合格者数の分析から不足分野の資格保有者をターゲットに設定できます。なお、正確な日程や詳細は必ず試験実施機関の公式サイトで確認しましょう。
キャリアアップシステムとの連携(CPD制度)
建設キャリアアップシステム(CCUS)は、技能者一人ひとりの資格や現場での就業履歴をデータベース化し、その能力が正当に評価される社会を目指すための仕組みです。
建設業振興基金は、このCCUSと連携し、CPD(Continuing Professional Development:継続的能力開発)制度の運営を支援しています。
なぜCPDが重要なのか?
CPD単位の取得実績は、単なる自己研鑽の記録にとどまりません。企業にとっては経営上の大きなメリットがあります。
・経営事項審査(経審)での加点: 公共工事の入札に参加する際に必要な経営事項審査において、技術職員のCPD単位取得状況が評価項目(W点)に含まれます。取得単位数が多いほど評価が高まり、受注競争で有利になります。
・企業の技術力の証明: 発注者に対して、自社の技術者が常に最新の知識を学んでいることを客観的に示すことができ、企業の信頼性向上に繋がります。
建設業振興基金の活用メリット
建設業振興基金の各種事業を戦略的に活用することは、企業に大きな競争力をもたらします。特に「人材育成」と「採用」の観点から、2つの主要なメリットを深掘りします。

【メリット1】資格取得・人材育成で助成金を最大活用できる
社員に資格を取得させたい、スキルアップを図りたいと考えても、コストがネックになるケースは少なくありません。建設業振興基金が窓口となる厚生労働省の「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コースなど)」は、この課題を解決する強力なツールです。
この助成金は、建設業の事業主が、雇用する建設労働者に対して技能向上のための実習(技能講習や特別教育など)を受講させた場合に、経費や賃金の一部を助成する制度です。
▼助成対象となる経費の例
・経費助成: 受講料、テキスト代、出張費など、事業主が負担した経費の一部(中小企業で最大3/4)
・賃金助成: 受講中の労働者に対して支払う賃金の一部(中小企業で1人1日あたり最大7,600円)
▼助成金活用のステップ
年間の人材育成計画を策定し、対象者と受講させる講習を選定します。
講習開始の1ヶ月前までに、管轄の労働局へ「訓練実施計画届」を提出します。
計画通りに講習を実施し、費用を支払います。
訓練終了後、2ヶ月以内に「支給申請書」と必要書類を提出します。
審査を経て、助成金が振り込まれます。
計画的な活用により、人材育成コストを大幅に削減し、より多くの社員にスキルアップの機会を提供できます。
助成金は後から申請することはできません。必ず訓練を開始する「前」の計画届提出が必須です。また、年度ごとに予算や要件が変更される可能性があるため、常に厚生労働省や建設業振興基金の公式サイトで最新情報を確認しましょう。
【メリット2】人材確保・採用力向上に役立つ
現代の求職者、特に意欲の高い若手や中途採用者は、給与や休日だけでなく「その会社で自分がどう成長できるか」というキャリアパスを重視する傾向にあります。
建設業振興基金の制度を活用した「資格取得支援制度」は、企業のエンプロイヤー・ブランディング(働く場所としての企業の魅力を高める活動)において、非常に有効な武器となります。
▼採用活動での具体的なアピール方法
・求人票での明記: 「監理技術者講習費用全額補助」「人材開発支援助成金を活用した資格取得サポートあり(玉掛け、足場、職長教育など多数実績)」といった具体的な文言を記載する。
・採用サイトやブログでの発信: 実際に制度を利用して資格を取得した先輩社員のインタビュー記事を掲載。「入社前は未経験でしたが、会社のサポートで複数の資格を取ることができ、今では現場を任されています」といったストーリーは、求職者に強いインパクトを与えます。
・面接でのプレゼンテーション: 入社後のキャリアステップとして、「1年目に○○の資格、3年目には△△の資格取得を目指しましょう。費用は会社が全面的にバックアップします」と具体的に提示することで、求職者の入社後の働く姿を明確にイメージさせることができます。
これらの取り組みは、「社員の成長に投資する企業」というポジティブなイメージを醸成し、数ある建設会社の中から自社を選んでもらうための強力な差別化要因となります。
建設業振興基金の注意点
制度活用にはメリットが多い一方、注意点もあります。まず、監理技術者講習や助成金申請には締め切りがあり、特に助成金は事前申請が原則です。計画から書類提出まで時間がかかるため、年間スケジュールを早期に立て余裕を持って手続きしましょう。次に、制度内容や要件は法改正や予算で変わる可能性があるため、必ず一次情報源で最新情報を確認してください。
さらに、資格者証や講習修了証の有効期限切れは業務停止リスクとなるため、期限管理とアラート体制が不可欠です。
建設業振興基金のよくある質問【FAQ】
建設業振興基金の会計処理・勘定科目の取り扱いは?
監理技術者講習の受講料や、各種セミナーへの参加費などを支払った場合、会計上の勘定科目は「研修費」または「教育訓練費」として処理するのが最も一般的です。これらは企業の経費として計上できます。ただし、企業の会計方針によって異なる場合があるため、最終的には顧問税理士にご確認ください。
合格発表はいつどこで確認できますか?
- 監理技術者講習: これは試験ではないため合格発表はありません。講習を修了すると、後日「監理技術者講習修了証(資格者証に貼付するラベル)」が郵送されます。
- 施工管理技士試験: 試験実施機関である「一般財団法人建設技術者センター」のウェブサイトで、指定された日時に合格者の受験番号が発表されます。
マイページ登録方法は?
監理技術者講習のオンライン申し込みなどに必要な「マイページ」は、建設業振興基金の公式サイトから登録できます。
トップページから「監理技術者講習」のセクションに進み、「新規利用登録」のリンクから、氏名、メールアドレス等の必要情報を入力してアカウントを作成します。一度作成すれば、申込履歴の確認などが容易になります。
まとめ
本記事では、建設業の採用担当者や経営者が知っておくべき「建設業振興基金」の役割と活用法について、多角的に解説しました。建設業振興基金は、単なる講習実施機関ではありません。
人手不足が叫ばれる今だからこそ、これらの制度を戦略的に活用し、社員が成長できる環境を整備することが、他社との差別化を図り、優秀な人材から選ばれる企業になるための鍵となります。
この記事が、貴社の採用戦略と人材育成計画の一助となれば幸いです。